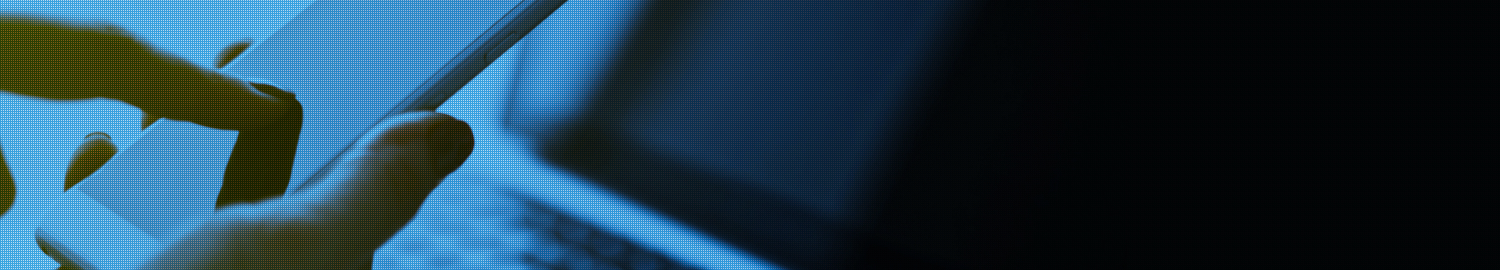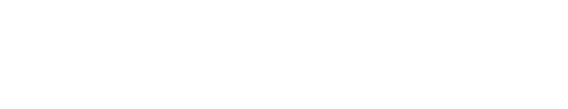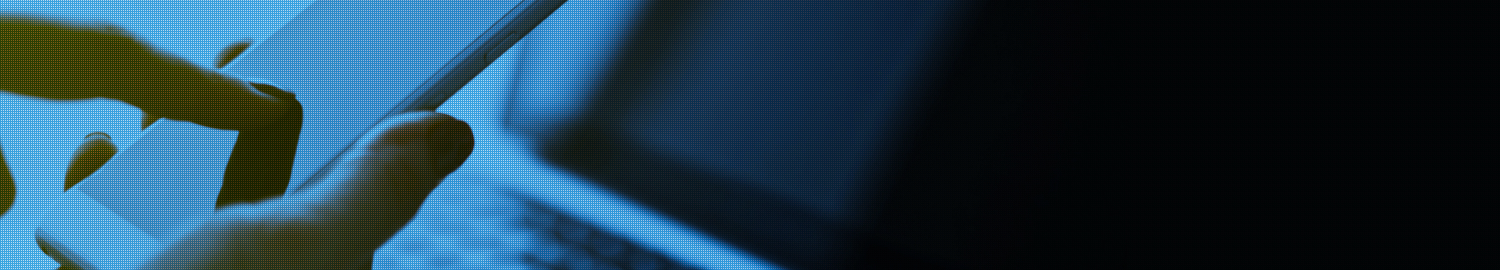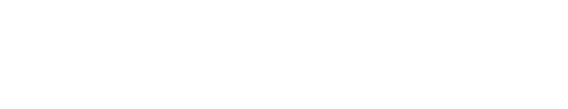労働現場での事故やトラブルを未然に防ぐことを目的に実施されるKY活動は、安全な職場環境を整えるために欠かせない活動で、多くの現場で実施されています。
今回は、KY活動とは何かをはじめ、その必要性、進め方について解説します。弊社で取り扱っているおすすめの製品も紹介していますので、KY活動に興味のある方や、職場の安全対策を強化したい場合には、ぜひご一読ください。
KY活動とは何?
KY活動とは「危険予知活動」のことで、作業現場における事故やトラブルを未然に防ぐために、作業開始前に潜むリスクや危険をあらかじめ予測し、対策を講じる取り組みを指します。建設現場や工場など、危険を伴う作業が多い環境で実施されることが多く、安全を確保するための基本的な活動です。
労働者の安全を守るだけでなく、作業効率の向上や事故発生による損失を回避するためにもKY活動は重要な取り組みで、事故や怪我が発生する前に潜在的な危険を認識し、適切な対策を取ることで、安心して作業できる環境を整えることができます。
企業にとっては労働環境の改善や法令遵守に繋がるため、KY活動は安全管理において欠かせない取り組みといえます。
KY活動の具体例

ここでは、KY活動の具体的な取り組みとして「指差呼称」「指差し唱和・ タッチ・アンド・コール」「健康確認」を紹介します。
指差呼称
作業対象や標識、信号、計器類などに対して指差しを行い、その名称や状態を声に出して確認する方法です。業界や事業場によっては「指差確認」や「指差称呼」とも呼ばれ、もともとは日本国有鉄道の蒸気機関車の運転士が信号確認のために行っていた安全動作です。
現在では、鉄道業だけでなく、航空業や運輸業、建設業、製造業など多くの業界でKY活動として行われています。
指差呼称は、単に視覚で確認するだけでなく、指差しと呼称という動作を組み合わせることで、作業者の意識レベルを高め、ミスの防止や集中力の向上に繋がります。「フェーズ理論」によると、指差しと声出しを行うことで、脳が活性化され、意識が前向きな状態に保たれやすくなると言います。
指差し唱和・ タッチ・アンド・コール
全員が一緒にスローガンやKY(危険予知)活動の確認項目を指差しながら声に出して唱和し、気合を一致させる手法です。朝礼や終礼の際に、スローガンやチーム行動目標を全員で確認することで、一体感と連帯感を高め、作業の安全意識を向上させる目的で行われます。
タッチ・アンド・コールは、スポーツの場面でよく見られるチームの気合を一致させる行動を、職場に取り入れたものです。バレーボールやサッカー、野球などで選手が手をタッチしたり肩を組んだりする行為がこれに該当します。
チーム全員がスキンシップを取りながら声を出し、連帯感を強化し、チームワークを向上させます。触れ合うことで、大脳の感情を司る部分にポジティブなイメージを植え付け、自然と安全行動を取れるようになる効果が期待できます。
健康確認
業務に取りかかる前に職員の健康状態を確認するのも重要なKY活動です。始業時のミーティングで職員自身が健康状況を自己チェックし、その結果を申告する方法が一般的です。
加えて、リーダーが職員一人ひとりの健康状態を観察し、問いかけを通じて把握することで、適切な指導や対応を行います。
このような健康確認は、職員のコンディションに応じた業務配分や対応策を立てる上でも重要です。
作業員の健康状態が良くない場合には、事故、災害につながるリスクが高まります。それを防ぐためにも、始業時の短時間のミーティングでリーダーが職員一人ひとりに対し、きめ細かな健康観察や問いかけを行い、適切な措置を取ることが求められます。
健康確認の結果、必要があれば医師への受診を促し、職員の意思と判断を尊重しながら、業務に適した役割や対応を決定することが事故防止に繋がります。
KYT基礎4R法の進め方

KYT基礎4R法は、職場や業務に潜む危険をチーム全員で発見・把握し、段階的に解決していくための訓練手法です。繰り返し訓練することで、一人ひとりの危険感受性を鋭くし、集中力や問題解決能力を高めることができます。
KYT基礎4R法の基本的な進め方を紹介します。
現状把握
作業現場や作業内容を具体的に理解し、どのような危険が潜んでいるかを考えます。全員で現場を見渡し、作業の流れや設備の状態を把握した上で、どんなリスクがあるかを一つ一つ洗い出すことが求められます。
作業員全員が積極的に意見を出し合い、些細なことでも共有することで、見逃されがちな危険要素を発見することができます。
危険ポイントの確認
次に、出された危険要素の中から、特に重大な危険箇所を選定します。全員で意見を出し合った結果を基に、優先して対応すべき危険ポイントを絞り込みます。どのリスクが最も作業や安全に大きな影響を与えるかを慎重に判断することで、効果的な対策を講じることができます。
この段階で危険を特定し、全員で「ここが危険だ」と明確に認識することが大切です。この取り組みにより、対策が必要なポイントを具体的に把握することができます。
対策の検討
特定された危険ポイントに対して、どのようにしてその危険を回避し、安全を確保するかを全員で検討します。具体的な対策案を話し合い、最も効果的で現実的な方法を選定します。
この段階では、実際の作業中に安全を確保するためのルールや注意事項を明確に定め、それを全員で共有します。対策は、実行しやすい形であることが重要で、また、従業員全員が理解し、守れるものにすることも大切です。
目標設定・実行
最後に、安全対策を確実に実行するためには、具体的な目標を設定します。この目標はチーム全体で合意し、共有されるべきもので、作業における全員の意識を統一する役割を果たします。
決めた対策を実行に移すための「チーム行動目標」を設定し、それを徹底して守ることが重要です。目標達成に向けて全員が責任を持ち、実施状況を確認するために指差し唱和などの安全確認方法を用いて全体の連携を図り、作業に反映させます。
定期的な進捗確認やフィードバックを行い、必要に応じて対策の見直しを行うことで、より安全な作業環境を維持することができます。
現場の安全対策におすすめの製品

株式会社大同機械では、現場での安全対策をサポートするための多様な製品を取り扱っています。
例えば、トラックの荷台への安全な昇降や作業をサポートする「
トラック昇降ステップ」、作業後はコンパクトに折りたためて収納時にも場所を取らない「
ライトステップ」といった折りたたみ式作業台もあります。
また、高所での作業中や昇降時の垂直移動での墜落を防止する「
安全ブロック」、障害物の多い現場で歩行者や作業員の転倒を防ぎ、安全な移動を確保するための「
セーフティブリッジ」なども提供しており、それらの製品を通じて、現場作業の安全性向上をサポートしています。
その他にも、現場のニーズに合わせた様々な製品を取り揃えておりますので、ご興味のある方はぜひ以下をご覧ください。
その他、安全関係の製品はこちら
労働災害を防ぐためにKY活動は重要
KY活動は、労働現場で事故やトラブルを未然に防ぐための重要な取り組みです。作業前に潜む危険を予測し、全員で対策を考え、共有することで、作業の安全性を高めることができます。
指差呼称や健康確認などの具体的な手法を取り入れ、危険感受性を高めることが大切です。KY活動を進めることで、安全な作業環境を維持し、事故を防ぐための意識向上が図られます。
現場の安全対策を検討している場合には、ぜひ取り入れてみてください。